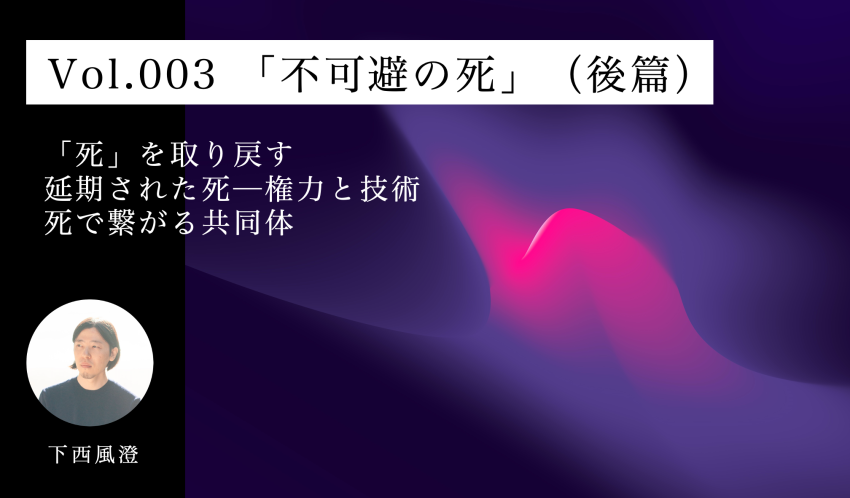人びとは死をどう扱っていいのかわからなくなっているのだ。なぜなら今日では死者であることは正常ではないからである。これこそ新しい事実である。死者であることは考えようもない異常なことであって、これに比べれば他のすべてのことは無害なものだ。死とは、ひとつの犯罪であり、癒しがたい異常なのである。
─ボードリヤール『象徴交換と死』
2020年4月、人々は死を強く恐れた。2020年5月、人々は死をすでに忘れた。
手のひらを返したような死に対する意識の急旋回に、僕は戸惑い、またその意味がよく分からなかった。しかし、留まっていたこのメルマガを書き上げていく途中で、だんだんとその意味が分かってきた。
■「死」を取り戻す
死に対する「過剰な恐怖」と「簡単な忘却」、これはその双方がある現実の裏返しなのだ。その現実とは死への無関心にほかならない。死への恐怖は死への心構えのなさから到来し、死への忘却は死への忌避から生じる。現代の人々にとって、まるで死は存在してはならない出来事かのように。
死は日常から遠ざけられた結果、僕たちの社会にはまるで死が存在しないかのごとく扱われるようになった。ボードリヤールは、現代にとって死は異常事態だと言った。しかし死は、本来もっと自然でささやかで、ありふれたものだった。
今世紀ほど、人間が死を忘れた世紀はない。人類は、時間をかけて死を遠ざけてきた。死を恐れて寿命を伸ばしてきたというだけではない。かつてヨーロッパでも日本でも、死者たちの埋まる墓は都市の内部にあったが、時代を経るにつれて墓は都市の周縁に、そして外部の土地へと遠ざけられたことは人類学ではよく知られている。核家族化が進み、死は葬式という儀式化された形式のなかだけで触れるものになっていった。
死は、多くのものをつまびらかにする。死は悲しいだけではない。そこには後悔や犠牲、あるいは憎しみさえも起こることがあるだろう。また、感謝や愛がいっそう芽吹くこともあるだろう。そうしたものすべてを引き取って、死を受け入れて僕たちは生きていく。
僕はいま「死を取り戻す」ことが必要だと考えている。しかし死は、そもそも自分のものであって、取り戻すも何もはじめから手元にあるのではないか。そうではない。歴史上、人間の死は巧妙に隠され、管理され、操作されてきたのだ。
だから、僕たちは一度、死を奪う構造を注視し、遠ざけられた死を取り戻すということの意味を考える必要がある。
■延期された死─権力と技術
ジャン・リュック・ナンシーというフランスの哲学者がいる。彼は死について思索した哲学者であり、自身も50歳の時に心臓移植を経験し、闘病しながら、自らの生命が技術によって延期されているという事実を実存的にも哲学した人物である。最初の問いは、なぜ自分は生き延びようとしているのか?であった。
「どうして生の持続は善なのか?当時わたしは50歳だった。この年齢が若いと言えるのは、20世紀末の先進国の住民にとってだけだ。わずか二、三百年前までは、この歳で死ぬのは少しも理不尽なことではなかった。」
ジャン・リュック・ナンシー『侵入者』(p.18)
ナンシーが言うように、人間の平均寿命はここ200年ほどで著しく長くなった。人類史初期の人間の平均寿命はおよそ25~30歳で、(比較的統計が正確にある)18世紀のフランスでもおよそ35歳前後、19世紀になっても45歳前後、60歳を超えるのは戦後の1950年以後だ。そして今でも、南アフリカでの平均寿命は約52歳である。