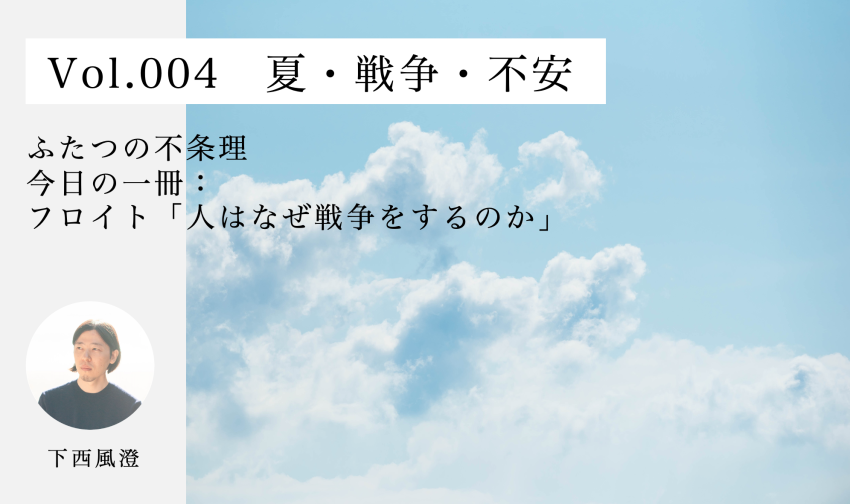これは、僕が2015年のある夏の日に書いた日記です。
…………………………………………………………………………………………
今年も暑い夏の日がもうしばらく続く。
青い空に、白い雲。ミーンミーンと鳴く蝉の声まで聴こえてくると、あまりに典型的な風景に、まるでどこかの小学生の日記の中に紛れ込んでしまったような気持ちがして、少し現実感がなくなる。
1945年のあの夏、空にピカッと光った人工の太陽に灼かれて瞬く間に死んだ人びともいれば、昭和2年の夏に「ぼんやりした不安」をもって死んでいった芥川龍之介のような人間もいる。
日本にいるとそのせいか、夏はどこか「喪の季節」のように思われる。春の終わりの生暖かい、あのぬるっとした風が死を運び、灼熱の夏に倒れていくのだろうか。移ろう季節と社会の濁流を横目に、僕は相変わらず随分と昔のことを考えている。
実家に帰ると、巨大なモールには何度もコピーされ擦れきった商品達が忙しなく並んでいた。本屋には、古代の哲学者が奇跡のように生み出し、数千年に渡って人間が守り続けてきた言葉の解説書の解説書ばかりが並び、服屋には異国のデザイナー達が命を削って作った服の、似たものの似たもので埋め尽くされている。これが僕たちが選択した幸福の光景である。それは、決して悪いことではない。
僕は最近、人類史というのは「不安への慰め」の歴史であったと考えるようになった。自然現象の過程のなかから気まぐれのように生まれた生命は、ある時にまるで「バグ」のように「意識」を獲得した。厄介なものだ。意識はただ生きることのみならず、いかに生きるのか、なぜ生きるのかという問いを自らに与え、しかもその答えは永久に得られない。人はそれを「不条理」と呼んだ。
不条理の悲劇には二つある。第一の悲劇は、あからさまな悲劇。私たちはいくら懸命に生きていても、時に巨大な震災によって、時に不治の病によって、何も悪いことをしていないにも関わらず、突如として命を奪われる。フランツ・カフカはグレゴール・ザムザを一夜にしてゴキブリへと変貌させてしまうことで、悲劇を喜劇へと変えようと抗った(『変身』)。