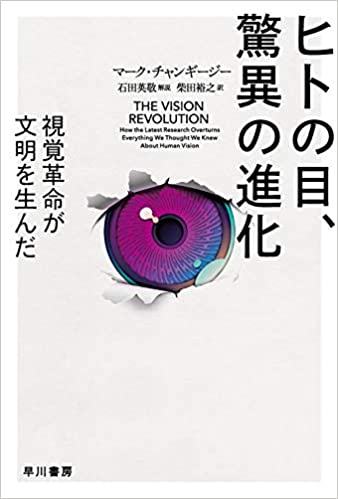■『都市で進化する生物たち: “ダーウィン”が街にやってくる』、メノ・スヒルトハウゼン (著)、岸由二、小宮繁 (翻訳)、草思社 、2020.
進化とは、数万年、数億年の時間をかけた自然の環境変化のなかで行われるものであると考えられている。しかし、近年の研究で、たったの数十年程度の環境の変化においても生物の生態が進化しうる可能性が指摘されている。著者は「都市」という急速な環境の変化が新たな生物の進化を促していると考える。
典型的な例はカラスが都市のなかでゴミの獲得のために知性を発達させている現象が世界のあらゆるところで見られるような場合だ。しかしこのような脳の発達による知性だけなく、たとえばコンクリートの多い場所に咲くタンポポが、種を遠くに飛ばしても子孫繁栄につながらないことから、綿毛を軽くする戦略から、自らの根ざす土に落ちることを想定したかのように、飛距離よりも繁殖力の高い種子を発育させる戦略に切り替えていると報告する調査などを紹介する。
都市という新たな環境で、生物は進化するのか。新鮮な事例とともに壮大な進化の理論を更新するかもしれない新たな試みが平易な口調で語られている。
■『ヒトの目、驚異の進化』、マーク・チャンギージー (著)、柴田裕之 (翻訳)、早川書房、2020.
2020年に文庫化された認知科学者マークチャンジ-ギーの代表作。なぜ人間の脳は、「文字」を読むための機能などなかったはずなのに、文字をすらすらと読めるのか?という素朴な疑問から、驚くべき仮説が次々に展開される。世界中の文字の形態を分析する著者は、文字の形態の特徴が、自然環境の認知的特徴点と至極似かよっていることを指摘し、人間の脳は自然を認識するために発達していたが、その機能を応用するかたちで文字を認識しているのではないかと語る。重要なことは、文字というそれぞれの各文化が勝手に創造したはずのビジュアルが、実は脳の機能に合わせて作られていたかもしれないという点と、逆に人間は文化をまるで環境と見立てるようにして脳のリソースを活用していたのかもしれないという可能性が指摘されていることだ。
同じく文庫化された『〈脳と文明〉の暗号: 言語と音楽、驚異の起源』では、「文字」のみならず、音楽と脳の関係を同じ観点から分析しており、こちらもスリリングでオススメ。
■『ニック・ランドと新反動主義 現代世界を覆う〈ダーク〉な思想』、木澤 佐登志 (著)、星海社、2019.
「新反動主義」という近年のアメリカで勃興しつつある「危険な思想」。資本主義とインターネットが世界を覆い尽くそうとしている現代の世界のなかで、そのようなある種の暴力に抵抗することが思想の役割であったはずが、むしろそれを肯定し尽くし、行くところまでアクセルを踏み続けることによって自壊させるのだという、危険だがカタストロフィーの快楽で誘惑すらする破滅的思想。
この思想そのものは到底肯定することはできないが、私たちは危険な思想を排斥するのではなく、むしろそこにこそ病理を認める必要があり、このような思想が生まれてしまったということ自体が重要な現代の課題である。著者の木澤氏の明快で魅力的な文章も、オススメする理由のひとつ。